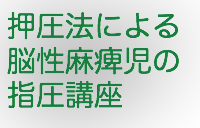![]()
第18回 押圧法概論(1)
始めに
技芸の習得には、勘や骨(シックスセンス)の重要性が語られ、“身体で覚える”とか“経験から学べ”と言った指導も少なくありません。もちろんこの意見に一理あることは認めます。しかし、押圧法とは、手指による種々の押圧操作によって、身体に生じる様々な作用を利用し、疾病の治療目的とする手技です。 〔押圧法っていったいな~に〕を参照してください。
〔指圧は芸術なり〕では押圧法の“芸術性”を述べました。確かに浪越徳治郎先生は天才的名人でした。 技は天賦の才を基礎とします。技術の基礎は理論です。理論は科学です。技師(わざし)は繰り返し事を行います。ここに技の理論化の可能性があります。技の理論を解明すれば、それは“技術”になります。押圧法も基本手技の理論的解明により、徳治郎先生の天才的な技が技術に変わると確信しています。
教師猫こと平島利文は、多年に渡り内弟子として、師匠浪越徳治郎先生の“天才的名人技”の直接的指導を受けた者の一人です。といっても、師匠の名人技を勘骨で学習することは全くできませんでした。そこで、患者さんを治療中の師匠の動作を徹底的に分析しました。さらに、“師匠の治療”という名目で指導を受けることができましたので、このとき様々な試みを行ないました。師匠への施術はその殆どが“腹部指圧”でした。師匠の腹部に置いた手を(師匠が手首をつかんで)誘導し、加圧部位や圧加減の指導を受ける方法でした。施術時間は30~40分位でした。その間は片足立ち姿勢で師匠の誘導のまま垂直圧で加圧部位や圧加減を変えなければなりません。自支の認識と共に、毎日の自支操作習練が欠かせなくなりました。指圧に対する言語による指導は殆どありませんでした。加圧部位の“ズレ”には寛容でしたが、圧方向さらに圧加減や加減圧速度については厳しく誘導されました。圧方向については“垂直圧の原則”に気付きましたが、圧加減や加減圧速度については感覚的に捉えられるも、理論分析はできませんでした。そこで意図的に手指操作の一つ一つに変化を加え、“誘導されなければ可”とし“誘導されたら不可”として分類し、不可が“何ゆえに不可”なのかを理論的に分析していきました。
押圧法の理論化やHPでの公表は、押圧法の技術継承を容易とし、疾病治療専門の医療技術としての認識を高め、養成講座受講生の押圧法学習習得にも有効と考えます。しかし、これらは上記したように教師猫こと平島利文が師匠の教えを基礎とし、医学知識や臨床経験を加え理論化した“私見”を多分に含みます。押圧法理論を不確立な状態で述べることに、ためらいもありますが、これらを“叩き台”として押圧法理論を確立していきたいと考えます。そのために、ここでは押圧法概論と題し、押圧法に関わる様々な内容を多面的に概説すると共に、様々な問題提起を行なっていきたいと考えています。
安全性の論拠
指圧治療の安全性について、『安全』と言い切られたり、『手指だけを用いて行うので、副作用がない』といった解説が行なわれますが、この程度の言葉で納得せず、“指圧の安全性”を疑ってください。
指圧の安全性を問われ、『指圧は、安全です』と言い切ったり、『おせば生命の泉湧く。ハッハッハー』と誤魔化すのは論外です。では、『手指だけを用いて行うので、副作用がない』という解説はどうでしょう。
副作用とは、“医薬”によって、治療の目的にそわないか、生体に不都合な作用が起ることをいいます。“医薬”とは治療などに用いる薬品を呼ぶ場合と医術と薬品の双方を呼ぶ場合がありますが、上記の『手指だけを用いて行うので副作用がない』という解説は、『指圧は薬を使わないので薬による副作用はありません』ということでしょうか。薬を使わず薬の副作用がでるはずはありません。“医薬”を医術と薬品の双方を呼ぶ用語と解釈し、副作用を治療の目的にそわないか、生体に不都合な作用が起ることと解釈すれば、『指圧は手指だけを用いて行うので、生体に不都合な作用が起ること(副作用)がない』とは言い切れなくなり、指圧の安全性の論拠は失われます。
〔備考〕
目的以外の魚が釣れた場合を釣魚用語で『外道』と呼びます。通常は“価値のない雑魚”ですが、時には“価値ある大物”が混じることがありますが、『外道』に変わりはありません。副作用は生体に不都合な作用を呼ぶ慣習が強くなっているようですが、本来は目的とする作用(主作用)以外の作用を呼びます。ある薬が心臓薬として注目され研究開発されたのですが、期待されていた心臓薬としての効果は弱く多毛という強い副作用がでました。現在、心疾患への副作用を持つ発毛剤として商品化されています。
『指圧は手指だけを用いて行うので、副作用がない』といった、大衆がイメージ的に抱く、“薬の副作用”に対する恐怖心をあおり、論拠のない安全イメージを植えつけようとする表現(行為)や指圧が無条件に誰が行なっても安全であるかのような“安全神話”の存在に、教師猫は疑問と憤りを感じます。
破壊すべき安全神話
指圧という用語は『指圧の心母心・おせば生命の泉湧く』というスローガンで浪越徳治郎先生の笑顔と共に日本から世界に、機械器具を用いず手軽にできる療法として広まりました。指圧の普及は良いことですが、指圧が“国家資格(免許)を必要とする医療行為”であることが伝わっていない感があります。
指圧を“業とするため”には、まず専門学校を卒業し、国家資格(免許)の国家試験受験資格を取得し、国家試験に合格し、免許を得なければなりません。国家試験受験資格の獲得(専門学校卒業)だけで、解剖学(210)・生理学(150)・衛生学・公衆衛生学(60)・病理学(60)・医療概論(30)・臨床医学総論(90)・臨床医学各論 I(90)・リハビリテーション医学(60)・運動学(30)・関係法規(30)・東洋医学論(60)・経絡経穴概論(30)・あん摩・マッサージ・指圧理論(90)・臨床指圧理論(60)・臨床指圧各論(60)・応用指圧実技(210)・東洋医学臨床論(120)・社会あん摩マッサージ指圧学(60)・基礎指圧実技(270)・臨床実習(48)・あん摩・マッサージ実技(60)・臨床医学各論 II(60)・課題研究(30)心理学(30)・社会福祉学(30)・
生化学(30)・栄養学(30)・生物学(30)・保健体育(60)英語(30)の必修30科目を最低でも三年間かけ合計2,208時間以上学ばねばなりません。この間も多くの試験に合格し、受験資格を得るのです。
上記の読むだけでも面倒になる、知識と技術を習得し、さらに国家試験に合格し、免許を得なければ、業とできないと、国が定める技術を“無知でも無害”と錯覚されてしまいそうな『安全神話』の存在・・・。
前を向いて、胸を張って『指圧は危険』と宣告します。危険であるがゆえに、必修30科目を三年間かけ、合計2,208時間以上学び、国家試験に合格し、免許を得、その後も知識と技術習得のため日々習練を欠かさない。これらの条件を満たして『指圧は安全で有効』といえる、医療技術となります。
〔指圧研究会・咲晩〕スタッフ養成講座受講生諸君
受講資格を指圧の有資格者および専門学校在学生やその他の医療従事者(有資格者)と定めている咲晩スタッフ養成講座の受講生諸君に、教師猫は、『高度な危険認識に対する意識』を要求します。
一般道路での車の運転には、運転免許の取得と注意力が伴えば、ほぼ安全は確保できると考えます。しかし、レースカーの運転には一般道路での運転とは、レベルの異なる知識と技術が必要と考えます。レースカーの運転(時速200~300kmの世界)の技術習得時に、一般道路(時速100km以下の世界)での“危険回避の経験や意識”を持ち込むことは“百害あって一利なし”ではなく、危険極まりない行為です。押圧法は、高度な医療専門技術です。手指操作の一つ一つにも、“安定した操作と精度”を要求します。
〔養成講座講師の受講生への対応〕
教師猫は、スタッフ養成講座で講師を務める〔指圧研究会・咲晩〕スタッフに対し、受講生の手指操作の細部にも目を配り、各自の実力に応じた『精度を指導し要求せよ』という指示を出しています。ですから、受講生諸君は合格点をもらえた前回同様の操作を行なっても、次回は注意を受ける結果となります。
微細な注意を受ければ受けるほど、受講生諸君の技術向上を講師が認めていると理解してください。講師から微細な注意を受け、指示に従うことが、技術向上の“最善の方法”であると心得てください。
 前のページ へ
前のページ へ