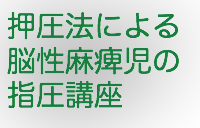![]()
禁止の禁止

はじめまして・・・。 投稿者:ぴょん吉 投稿日:2005/05/06(Fri) 02:37 No.619
こんばんは。はじめて書き込みします、ぴょん吉と申します。
友人から「おもしろいところがある」と教えてもらい、やってきました。
私は「鍼灸師」です。こちらは「指圧師」の方ばかりのようで、書き込みはちょっと心苦しいのですが・・・
お邪魔します。
まずこちらの膨大な資料に驚きました。
興味深い項目はたくさんあるのですが、先ほど脳性麻痺についての記述を読ませていただきました。
『人は“あらゆる能力を学習しなければ得られない”』『禁止語』のこと、『学習していないものは思い出せない』・・など、聞いたことが無いようなお話ばかりでした。
さらに、私たちが考えている『指圧』と、こちらで言う『指圧』とは ずいぶん隔たりがあるようだと思いました。
正直なところ、指圧で脳性麻痺の症状に変化が出せるとは思っていませんでした。(ごめんなさい・・・)
鍼灸では、運動障害に対して「通電治療(いわゆるパルス治療)」で筋肉に電気刺激を与えたり、太くて長い中国鍼を刺したりします。(主に、脳梗塞の後遺症の方が多いですが。)
つまり、通常よりも強めの刺激を与えます。
しかしこちらの『指圧』では強い刺激は不要のようですね。
『押圧法』『ディファンス』『腹部指圧』・・・
あまり聞いたことが無い言葉ばかりで、なかなか読み進むことができません。
でも、ものすごく重要なことがたくさん書かれていると思いますので、また来たいを思います。
だらだらと書き込み、失礼しました。
Re: はじめまして・・・。 投稿者:教師猫 投稿日:2005/05/06(Fri) 21:49 No.621
ぴょん吉さん。ようこそ。ようこそ。ようこそ。
>私は「鍼灸師」です。こちらは「指圧師」の方ばかりのようで、書き込みはちょっと心苦しいのですが・・・お邪魔します。
書き込み大歓迎します。
実は教師猫、鍼灸刺激には強い関心があるのです。
以前、こちらの先生に奇問・愚問をぶつけてお世話になりました。
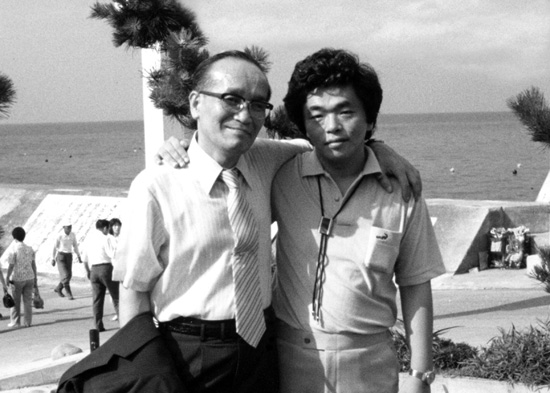
現在も某鍼灸学校の校長先生を困らせております。
罪滅ぼしに教師猫がお答えできる質問には答えます。
『わかりづらくて、肝心な所が書いてない』と自認してHPの内容です。
諸事情で書き辛いことも、質問があれば答えることができます。
ぜひ『質問を土産に』遊びに来てください。待っています。
なぜ指圧のHPに鍼灸の大家... 投稿者:ぴょん吉 投稿日:2005/05/16(Mon) 00:20 No.628
こんばんは。ぴょん吉です。
先日の書き込みにお返事をくださり、ありがとうございました。
しかしその中にやけに見覚えのある方の写真がありましたね。
おそらく、左側のネクタイをしている方は、鍼灸の大家、芹沢先生ですよね?
私も著作の写真などでしかお目にかかったことはないのですが。
ということは、右の方が教師猫さまでしょうか。
芹沢先生のお姿から見ると、かなり昔の写真のようですが・・・。
教師猫さまも鍼灸治療に関わりがあるのでしょうか??
「現在も某鍼灸学校の校長先生を困らせております。」とありましたが、どちらの校長先生のことでしょうか・・・気になります!
今日は質問をさせてください。
「教師猫は、~ません。3」のページで、最後に「愁訴改善のための禁止事項を禁止しません。」という項目がありますよね?
私はこの文章をざっと読み、もう一度読み、さらにじっくり読みました。
でも、何のことかさっぱり意味がわかりませんでした(泣)。
反響があれば続きを検討してくださるとのことでしたので、もしよろしければ具体的な解説をお願致します!
Re: なぜ指圧のHPに鍼灸の...投稿者:教師猫 投稿日:2005/05/16(Mon) 14:29 No.629
ぴょん吉さん。こんにちは。
質問持参の書き込みをありがとう。
>しかしその中にやけに見覚えのある方の写真がありましたね。
>おそらく、左側のネクタイをしている方は、鍼灸の大家、芹沢先生ですよね?
>私も著作の写真などでしかお目にかかったことはないのですが。
>ということは、右の方が教師猫さまでしょうか。
おっしゃるとおり、鍼灸の大御所と言うより、日本を代表する東洋医学の第一人者である芹沢勝助先生と教師猫のツーショットです。
>芹沢先生のお姿から見ると、かなり昔の写真のようですが・・・。
>教師猫さまも鍼灸治療に関わりがあるのでしょうか??
「鍼灸師」のぴょん吉さんに芹沢勝助先生についての説明は避けますが、芹沢勝助先生からご指導頂いたのは『鍼灸』ではありません。
先生には「あん摩・マッサージ・指圧理論」や戦後の法制化などについてご教授いただきました。
身分をわきまえず、礼儀知らずの教師猫は、機会あるごとに、追い回し、質問を繰り返し、大変ご迷惑をお掛けしました。
特に「指圧理論」や「指圧の法制化」に対する質問には、奇問・愚問をぶつけ閉口されたと思います。
ぴょん吉さん。
教師猫は指圧師で鍼灸治療については、無知な者と判断されて、今後もお付き合いください。
>「教師猫は、~ません。3」のページで、最後に「愁訴改善のための禁止事項を禁止しません。」
>という項目がありますよね?
>私はこの文章をざっと読み、もう一度読み、さらにじっくり読みました。
>でも、何のことかさっぱり意味がわかりませんでした(泣)。
>反響があれば続きを検討してくださるとのことでしたので、
>もしよろしければ具体的な解説をお願致します!
「教師猫のポッケ」は、教師猫のカラーが強いので、あまり真剣に読まずに、読み流して下さい。
お約束ですから、質問の返答は近々れいの場所に書き込みます。

お答えします。
抜粋して読んでください
疾病治療の過程において、禁止事項は数多くありますが、愁訴改善のための禁止事項を教師猫が禁止することは稀です。理論的には疾病治療の妨げとなる行為を禁止することは重要だと考えます。しかし、医学的には禁止事項であっても、患者さんにとって容易ではない内容が少なくはありません。疾病治療目的ではなく、治療家の自己弁護を目的と感じられる内容もしばしばです。
ぴょん吉さん。 上記は、教師猫の~ません。3【愁訴改善のための禁止事項を禁止しません】の内容を抜粋したものです。どちらがわかりやすいですか。時に、教師猫の文章は抜粋して読んでください。
誰でもわかる、無用な注意
患者さんとは、ありがたいものです。腰痛患者に「腰に負担のかかる重いものは、持たないように 」と、誰にでもわかるような、当たり前の注意をしても、「持てと言われても、腰が痛くて持てません」と言わず「ありがとうございます」とお礼を言ってくれます。こんな、誰でもわかる無用な注意でお礼を言わせず、「物を持つときは、(感覚で)重さを量って持ちなさい」とか「体に言い聞かせ、声に出して持ちなさい」と禁止事項を並べるのではなく、危険回避の行動法(物の持ち方)等を専門家として指導してください。
〔ヒント〕
事前に体に言い聞かせ、動作に移ることは危険回避に有効です 。介護で「寝かします」、「起こします」の一言が患者さんの体位変換に伴う脳貧血や過緊張さらに不安や苦痛等も予防することができます。
意味不明な注意
患者さんに「お大事に」といたわりの声をかけることは大事ですが、「無理をしないように」といった意味不明な注意は如何なものでしょう。「何処からが無理ですか」と問い直す患者がいないので幸いですが、問い直しに答えを用意していますか。「(立ち木の枝を)可能な限り、折れないところまで無理をしないで曲げなさい」と指示して「なぜ折った。無理をするなと注意したのに、お前の責任」と言うようなものです。
患者さんに、「無理をしないように」という言葉に代表されるような、もっともだけど曖昧で抽象度が高く、患者さんが事前に自己判断できないような指導や(予測される悪い結果に対する)治療家の責任回避とも受け取れる自己弁護的な注意を「意味不明な注意」と呼んで、嫌います。教師猫は「無理の数値化」と呼びますが、患者さんが無理か否かを判断できる、具体的判断基準を示した指導を行ってください。
教師猫がここで説明を終えた場合に、教師猫の解説は「もう十分」でしょうか「意味不明な注意の代表」と非難を浴びるのでしょうか。顔の見えない相手に解説することを苦手とする教師猫のツブヤキです。
【教師猫流「無理の数値化」】
教師猫は患者さんに、「無理の測り方の物差」による、自己管理を指導します。「無理の物差」は個人用で疾患や症状、個人差などによって異なります。腰痛患者の「無理の測り方の物差」の一例をあげます。腰痛などの激痛時は患者自身も安静を求めますので、あまり使用しませんが、緩和期の自己管理には有効な結果が出ています。内容に個人差を加味することを含んで参照してください。
「無理の測り方の物差」の一例。
・2~3分間で苦痛が生じる姿勢は「無理な姿勢」とし、5分以上継続することにより苦痛が生じる姿勢は「継続が無理な姿勢」、1分以内で苦痛が生じる姿勢を「無茶な姿勢」に分類する。
・動作も姿勢同様に、「無理な動作」・「継続が無理な動作」・「無茶な動作」に分類する。
・苦痛が生じない動作については、発症以前の80%を超えれば「無理な動作」、100%を超えれば「無茶な動作」に分類する。
・動作や姿勢の継続時間も苦痛が生じない動作同様に、「継続が無理」・「継続が無茶」に分類する。
・発症前は日常的負荷の行動であっても、1ヶ月以内に行なったことがなければ「無理な行動」、3ヶ月以上行なったことがなければ「無茶な行動」と分類する。
「無茶」は全面禁止とするが、患者自身が自制する内容なので、執拗に注意せず、簡単な告知とする。「無理」に対する対応は、安易に禁止せず、個人差を十分に加味し、患者さんの社会的な役割を著しく損なわないように考慮し、「無理」を自覚させ、「無茶」に至らない対応や事後処理の条件を指導する。
教師猫的には、患者さんが“社会的役割を損なう”結果を招く禁止は行なわないことを原則としている。結果として「無理」を承知で認める傾向があるが、患者さん自身に十分に「無理」を自覚させ、「無茶」に至らない対策として“無理は治療回数”で補う対策を取っています。(腰か財布が痛いかは患者の選択)
「何もしないように」という注意
患者さんの「体のために○○を始めたいのですが」といった問いに、「何もしないように」と指導するのが教師猫の常です。腰痛の患者さんから「腰痛緩和の目的で腰痛体操を始めようと思うのですが」とか「腰痛は背筋や腹筋の筋力低下が原因と学んだので、筋力増強のトレーニングを始めたい」などという質問に対する教師猫の返答は、殆んどが『NO』です。腰痛体操とは“腰痛予防体操”です。発症前なら有効でしょうが、発症後に行うには負荷が不適で、危険性を多く含んでいます。まして、指圧で治療中の患者さんには不要です。筋トレも同様です。腰痛原因のなかに筋力低下が関与することは認めますが、腰痛原因を筋力低下のみで語れるものではありません。腰痛には自覚症のみならず多くの他覚的症状が診られます。臨床現場で腰痛患者の他覚的所見に、拮抗筋や協力筋あるいは単関節筋と多関節筋または左右の同一筋などにアンバランスを認められないことは極めて稀です。
筋電図検査を行なえば、筋の収縮効率のアンバランスが確認され、超音波検査では過伸展抑制機能のアンバランスを観察することができます。先に述べた筋の太さのアンバランスはMRI検査で明確です。腰部MRI(大腰筋)画像を参照してください。なお、これらは指圧治療における診断法(視診や触診等)で他覚的診断が可能です。他覚的診断によって得られた情報を患者さんに提供し、十分に説明すること。
患者管理も臨床現場の指圧師の重要な課題です。これ以上の説明は蛇足と考え、控えますが、炎症が現存し、筋の様々なバランスが乱れている腰痛患者に、教師猫は「何もしないように」と注意をします。
患者さんが「健康のために何かをした方がいいのでは」と問いかけると、教師猫は、決まり文句のように「何もしないように」と答えます。理由は、患者さんの問いの源が“器官の存在感”に由来するからです。行動発心理由が危険要素を含む“器官の存在感”でなければ、教師猫は運動法を細かく指導します。
自覚症状改善期の注意
患者さんから『注意事項』を求められても、特別に「何もしないように」と返答することが多い教師猫が、執拗に注意を促す時期があります。それは自覚症状の著しい改善期や消失期に対応する注意です。
患者さんの疾病意識は『上り坂で荷車を引く』状態と似ています。上り坂では細心の注意をはらい懸命に荷車を引きますが、自身の体が頂上に達すると眼下が開けます。「やっと、登った」といった安堵感と共に注意が散漫となりがちです。この時、引き手の体は頂上ですが、荷車の重心はまだ坂の途中です。あと、一歩か二歩を注意深く前進すれば、無事荷車の重心は頂上に達します。これは自覚症状の消失を疾病治癒と思い込む患者さんへ注意を促すときの例え話です。
自覚症状の消失を疾病治癒と思い込み、安堵で注意が散漫となったとき、思わぬ落とし穴があります。初診時から他覚的診断による他覚的自覚を患者さんに促し、自覚症状の変化に一喜一憂しないよう、痛覚の生理(過敏・鈍麻)も必要に応じて説明し、他覚的診断に裏打ちされた禁止事項の提供や指導に心がけてください。教師猫が、執拗に注意を促す時期の説明は、蛇足と感じましたので略します。
ぴょん吉さん。
教師猫としては、具体的な解説を書いたつもりです。しかし、教師猫の教師猫的文章ですから・・・
再質問は、ぴょん吉さんに限らず、何方からでも、何度でも受けます。掲示板に書き込んでください。