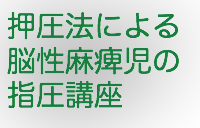![]()
09・教師猫は、〜ません(5)
疾病治療を業とする教師猫への依頼は、(患者さんが抱える)疾病の治療です。このとき、“病魔”は敵ですが“患い人”である患者さんは教師猫と共に“病魔”と戦うパートナーです。病魔との闘いにパートナーシップは不可欠です。しかし、“患い人”と治療家とのパートナーシップには思わぬ異変が生じます。時には教師猫への反逆・裏切りとも受け取れる事態が数多く生じました。臨床の現場から、それらが患者さんの治療家に対する裏切りではなく、“病魔”が“患い人”の心を味方につけてしまった結果であることを教師猫は知りました。
教師猫の治療室では、これらの異変を防ぐための慣習がいつしかルールとなっています。
わかろうとはしません
患者さんに「先生が私の苦しみを一番わかってくれる」と言われ、「わかってはいません」と答え、「所詮、他人事ですから、わかろうとしていません」と言葉を続ける教師猫がいます。「患者さんの苦しみを理解するのが治療家なのに・・・」言うに事欠いて、患者さんに向って“他人事です”とは不届き千万と叱咤されるでしょう。教師猫も最初は、患者さんの苦しみを理解しようとする努力をしました。しかし、風の中の羽根のように変化する“患い人”の心を理解することはできません。 教師猫にわかるのは、他覚的診断による患者さんの身体的異常とその変化です。これらを基に患者さんの身心の苦痛を推し量り、患者さんの苦しみを想像することはできますが、所詮は想像です。現実の苦しみを抱く患者さんに、想像で「私はあなたの苦しみがわかります」とは、教師猫は如何に叱咤されても言えないのです。
ある患者さんが、自身の母親から体調の愚痴を数日電話で聞かされ、ほとほと嫌になったとこぼした後に、「(先生は)どうして、あんなに沢山の愚痴を聞けるのですか。毎回毎回(私だけでも)相当な愚痴を言った」と問いかけてきました。 さらに、「(私の)愚痴のひとつひとつを丹念に聞いて、全てに丁寧に答えてくれた。あんなことが、なぜできるのですか。」と質問は続きました。この患者に限りませんが、長期に渡り、毎回毎回、愚痴を聞かされ続けることは稀ではありません。こんなとき、教師猫が愚痴の一つ一つを丹念に聞いて、全てに丁寧に答えることができるのは患者さんの苦しみを“わかろうとしていないからこそ”できるのだと答えます。苦しみの渦に巻き込まれれば、冷静な判断など到底できません。
仮に、治療家が患者さんの苦しみを全て理解したとしても、患者さんの苦しみが解決されるわけではありません。患者さんの苦しみを理解しようとしすぎると、己の未熟さに真正面から立ち向かう結果になりかねません。教師猫は己の未熟さに真正面から立ち向かい、何度も両刀論法や自己嫌悪に陥り、何度も痛い思いをし、己の未熟さに真正面から立ち向かう愚かさを学びました。患者の苦しみを理解しても解決されるわけではありません。しかし、丹念に聞いて、丁寧に答えることには意義を感じます。教師猫がやるべきことは、苦しみの理解ではなく解決手段の模索です。そこに、教師猫が“戦う土俵”があると確信しています。
治療家の教師猫は“自我自賛”を通り越し、自身でもあきれるほど、忍耐強く怒りません。しかし、夫や父親としての教師猫は少し?異なるようです。娘のえのきに「父さんはかなり気が短いかな?」と質問してみたら、えのきから「気が短いとはいえない」と言われました。えのきの説明では“気が長いか短いか”ではなく、短いということはそこにわずかでも時間がある。父さんにはそれが無い。だから、怒るまでに時間の無い人を“短い”とはいえない。実に的を獲た回答です。どうやら、教師猫の正体は単純な感情だけの単細胞のようです。
反応しません
治療中に、患者さんが突然涙ぐんだり、泣き出すことがありますが、このことに、教師猫は全く反応しません。涙を拭くために、治療用のハンカチを差し出すことはありますが、淡々と施術を続けながら、患者さんが泣きやむのを待っています。患者さんが泣き止めば、再び教師猫のお喋りが始まります。絶対に“泣き出した理由を問いかける”ことはありません。奇異に感じられるかも知れませんが、これも教師猫の治療室での長い慣習なのです。
患者さんが突然涙ぐんでも泣き出しても、理由を問わないでください。もちろん、突然泣き出すには理由はあるはずです。しかし、問わなくても、患者側が話したければ、泣きながらでも話します。治療室で安堵の涙や患者さん自身にも意味不明な涙がわけもなくあふれることは日常です。問わないでください。問われれば涙の言い訳を考えなければなりません。
リラックス効果を得るために、笑ってみてください。「おかしくないのに笑えない」といわず、笑ってみてください。笑っているうちにおかしくなります。笑いには積極的なリラックス効果があり、積極的に笑うことで、リラックス効果を得ることもできます。笑いより深いリラックス効果を得るためには、泣くことです。「笑いは表層・涙は深層」といわれるように、涙は心の奥深くからあふれ出し心を洗ってくれます。しかし、涙が笑いより深いリラックス効果が期待できることがわかっていても積極的に泣くことは・・・なかなか容易ではありません。
突然患者さんが泣き出せば、戸惑いを感じると思いますが、深いリラックス効果を期待し、気兼ねなく、自由に泣ける場所を提供してください。理由は最後まで問わないでください。問われれば、患者さんは涙の言い訳を考えたり、気恥ずかしさを感じなければなりません。これではリラックスの効果や効率が下がります。教師猫は、患者さんのリラックスの邪魔をしないために、患者さんが突然泣き出しても平然と無視し、全く反応しません。
原稿作成の途中で患者さんに「私は(患者さんが)泣き出しても無反応だろう」と問いかけたところ、「違います、先生は(時に)積極的に泣かせます。」と返答されました。どうも藪蛇だったようです。こんなこともよくあります。患者さんが泣きながら相談電話をかけてくることがあります。そんな時、教師猫は“まず先に十分泣くこと”をアドバイスし、一旦電話を切り、十分泣いてから改めて電話を受け付けます。〔その後の相談への対応がスムーズです〕
 前のページ へ
前のページ へ