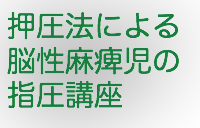![]()
第13回 最小スタンス感想文
咲晩スタッフ感想文(最小スタンス)
最小スタンスに対する咲晩スタッフ20名分の感想文を〔2004年4月指圧研究会・咲晩講習会記録〕より
抜粋して掲載します。参照資料ですから、くれぐれも上を見ないようにしてください。
〔感想-A〕
最小スタンスはやった後に、標準に戻すと前足がすごい楽に押せるようになる。ただ最小スタンスだとバランスとるのが大変なのでしっかり練習していかないといけないと思った。実技の時、何か他の人達がすんなりこなしていくのを見て、置いていかれているような気がすごくした。日頃からしっかり練習して行かなくてはと改めて思った。
〔感想-B〕
最小スタンスでの練習でしたが、その日講習が終った時から膝ではなくモモが2日間笑いっぱなしでした。翌日に、父親を最小スタンスを意識しながら指圧しました。モモがぷるぷるしましたが下半身が安定している時の指の感覚の違いにびっくりしました。疲れて、気を抜いたまま最大スタンスで始めると、だんだん指が入っていかなくなるのが分かったのと、下半身と上半身がバラバラにうごいているのを感じました。最小スタンスで押すと「手首のしめ」のような「下半身のしめ」を感じました。しかし、下半身のしめを感じると同時に手首・四指のしめがいかに甘いかにも気付かされました。
〔感想-C〕
「支点を定めない訓練のための最小スタンスの訓練」は、現時点の私たちが押圧法を習得するためにとても有効な訓練方法だと思います。午後の終わりごろに、メンバーが最小スタンスの訓練をしている光景を見て、以前とは比べ物にならないほどに姿勢が安定しているのが分かりました。ただ、さすがに次の月曜日、火曜日は大腿前面がパンパンで、階段を降りたり、しゃがんだりする動作が辛かったです。
〔感想-D〕
正しいスタンスから正しい加圧が得られる。まだまだ、自分の中ではスタンスと加圧がばらばら、別々のもので一つになっていません。小さなスタンスの崩れが、圧を不安定にしてしまうことをよく頭に入れて練習しなければと思いました。
〔感想-E〕
最小スタンスの感想、最初は「なんだろ?」と思ったし、よろつくし、足は痛いし…足首を使ったり、つま先を立てたり、奥深いですね(たぶんもっともっと…深そう)午後、先生に見ていただき、午前より慣れてきたところで最小スタンスから通常スタンスへ切り替えたとき、きれいだったと思います。でも安定していないとできないと先生が言っていました。まさに、その通りだと思いました。
〔感想-F〕
実技は、最小スタンスで、上半身は変えずに下半身の動きで、押す点を移動させるということで行いました。先生に指導していただくと、下半身にうまく力がはいり、上半身・腰などの力がきちんと抜けて、これほど上半身が自由になるのだと感じました。しかし、なかなかうまく下半身に力が入らない状況です。腰に力が入ってしまいます。(腰に力の入った状況を長く我慢できるようになったなと思ってしまいました。根本が間違っているなと思います。)腰がほとんど動けない状況で、今回も大変難しく思ってしまいましたが12月の実技のつづきと思うと来月まで移動の練習をがんばろうと思います。いままで、安定するスタンスということを考えてしまっていましたが、今回から下半身で移動ということを意識しようと思いました。前回より2ケ月使いにくい左手のボールの練習時間を多くしてみたのですが、なんとなく右手に近づいた感じになり、ボールはすごいと思いました。
〔感想-G〕
最小スタンスの練習、型的にはただ足幅を狭くしての事だが、そこから学べる事が沢山あるのにはただただ驚きの連続だった。動ける幅が狭いからこそ無駄な動きが出来ない、当然足場が狭い為より安定性が求められ、それを上手く出来るようにする為の足首の締め。スタンスを狭くするだけ色々な事が見えてくる。指圧って面白いなと久し振りに思った。
〔感想-H〕
最小スタンスをやった次の日、患者さんを押していて以前より、姿勢の安定感が増しました。また、患者さんの手の位置などをなおさなくても、こちらからわずかなスペースにもぐりこんで、押圧することもやりやすくなり、動きの自由度が増した感じがしています。支点を定めないということの意味がまだ分かりませんが、最小スタンスをやったあと、両足の間に体が浮かんでいる感じで方向変換がやりやすくなりましたので、こういうことかなあと今は思っています。受けの体側で押すとき、受手の頭部中央に目線をもっていくという指示で、スタンス時の迷いの一端がはっきりとした感じです。
〔感想-I〕
今回の講義で最小スタンスを教えてもらい、次の日から病院でも使いはじめてみました。大腿部が最初の時よりきつくなく狭いベッドではやりやすかったことに驚きました。しかし移動動作がうまく出来ず腰をひねったりすることが多いので注意しながらやっています。
〔感想-J〕
最小スタンスですが、骨盤がロックされ、力が逃げずに押せる感じでした。ただ自分自身の腰回りのバランスが悪いようで、どこかで引っかかってしまう。練習していくしかないと思いました。
〔感想-K〕
最小スタンスはもう少し早く教えてくれれば・・・。今、働いている病院に横幅が、約1メートル、高さが膝下ぐらいまでのベットが置いてあります。今までは、ベットの上で最大スタンスで指圧をしてました。尻尾のことを考えると、どうしてもバランスが崩れてしまい、はっとすることが多々ありました。今は最小スタンスで指圧をしているので尻尾をあまり動かさなくていいので、バランスを崩す事も少なくなりました。が、やはり上手く指圧をするのは難しいですね。
〔感想-L〕
今までスタンスの練習をしていても、腰の位置が定まらず、どの位置が自分にとって、体の向きと並行なのか、腰が引けているのではないか、等これでいいのかなと思いながら練習していました。今回の最小スタンスは動きが思うようにならないからか、腰の位置が定まり、これだったら悩まずに練習できるかもしれないと目の前の霧が晴れたような気がします。ただスタンスの練習があまり出来ていないので、きつく筋肉痛になります。
〔感想-M〕
最小スタンスは、午前中、体重移動がうまくいかない、しっぽがうまく使えない大腿部が疲れる、体のあちこちがぷるぷるするという感じで散々でした。しかし午後になるとどうにか形になってきて、終わるころには体を楽に動かせるようになり、むしろ最大スタンスよりも集中するかもと思いました。ふと周りを見ると、補佐の人たちも午前よりずっとキレイなスタンスになっていました。どんどん追いついてくるなあ、といつもながらヒヤヒヤします。最小スタンスにすると、しっぽの重要性が本当に強く感じます。しっぽでふんばる、しっぽを使って体重移動をする、ことを難しく感じるのですが、後から最大スタンスをやってみると「こんなに楽なものなんだ」と思いました。講習会後はみんなで「なんか今日は体がだるいね。」といいながら帰りました。最小スタンスで脚が疲れたせいか、実技で受ける時間がたっぷりあったのでその効果だったのかはわかりませんが。「支点を定めない押し方」というものが実際押してみるとわからなくなります。膝とか腰とか肘とか、どこか1点に頼りたくなってしまいます。ふらふらしそうで不安になります。でも先生の柔らかいスタンスの動きを見ると「ああ、定めていないんだ」、と思います。
〔感想-N〕
最小スタンス訓練・すべては、「訓練不足なのだ!」と思う。地面を蹴られない。最大スタンスでもしっぽが地面にしっかりついていない。それゆえ肩に力が入る。手指がおろそかになる。すべてはバランスなんだと思った。プロの人がどんな職業でもバランスで毎日くり返しがんばれる。特定のところばかり変に力が入っていたのでは、生涯くり返すことは無理だろう。
〔感想-O〕
支点を定めぬ訓練の基本として最小スタンス姿勢による実技指導を受けました。頭の中を「皆のレベルが向上したので最小スタンスの練習を許可します」と言われた先生の言葉が渦巻いています。最大スタンスの幅を狭めただけなのに身体が動きません。身体のあちこちがイタイ、ダルイ・・・動作がバラバラです。「圧の安定やスピーディな動作。腰部、下腿の疲労防止や将来の重心(横)移動に欠かせない技術・・・」ただ、ため息です。先生のデモを思い出しながら、またまた、ため息です。頑張ります。頑張らねば!! 不思議なことに最大スタンスがすごく楽です。スムーズに動きます。頑張らねば!!!
〔感想-P〕
最小スタンスについてですが、目的は"支点を定めないためのスタンスの訓練"と言うことでしたが、やってみて、とても不安定で大腿四頭筋がツラく(翌日は筋肉痛)これはいやでも指先のセンサーに集中するためには、全身のあらゆる支点となりうるところへ、意識が向かわざるをえないのではと思いました。どこを支点にするかを頭で考え、判断するよりは、むしろ瞬時に体自身に任せて判断させるように、ならざるを得ないのかもと考えました。以前にピアノの鍵盤をたたいて音を出すことをたとえに出して、話をして頂いた時に支点を定めないでつまり無理な力を使わないで結果(音)を出すと意味かと捉えていたのですが、むしろこれは、施術において術者自身の体に無理させない為の方法を身につけるという事が、対する患者において最良の結果を出せるということではなかったかと少し考え方が変わったように感じました。
〔感想-Q〕
最小スタンスについて。足指、足底(母子球のライン)、足背、足首の使い方を修得するにはよい方法だと思いました。足が使えるようになるとスタンスの安定感が増し無駄な動きがなくなるなと感じました。使えるものはうまく使えるようにして効率よく身体を動かしてやれと思ってやってます。また、患者がそこにいると想定して、そこまでいけるか、いけてもそこで押せるか、ということを考えながら練習しています。しっかりとした土台でありながら自在に動けるということは今更ながらとても難しく、修練のいるものだと感じています。質問です。後ろ足の膝下腿のどの辺りが接地しているのがベターなのですか?
【A】 しっかりとした土台でありながら自在に動ける接地がベストです。
また確認ですが、最小スタンスの練習は筋力トレーニング(特に大腿四頭筋)ではありませんよね?もちろん筋力が必要ないと思っているわけではありません。あくまで足をうまく使える感覚を身につけるためと理解したのですが?
【A】 そのとおりです。
〔感想-R〕
やっと最小スタンスの登場かと、まず思いました。どう使うのかと思っていましたから、はじめはバランスをとる事も難しく、前足の大腿前側がものすごくつらかったです。その代わり、いつも腰が痛くなる(前足側の腰)のに、腰は痛くなりません。先生の説明で、最小スタンスは、腰をひねらない事がわかりました。
【A】 全てのスタンスで腰はひねりません。
その後のつま先を立てる場合と立てない使い方で、立てない方は、引っぱる感じがなんとなくわかりましたが、立てる方は、使い方がわかりません。先生から、つま先を立てた時の使い方ができていないから、腰がたおれる?様な事を言われましたが、ぜんぜん理解できませんでした。とりあえずいろいろやってみようと思います。・・・が、講習会の次の日、大腿前側が筋肉痛。昼ごろから腰が痛み出し、あれから1回も、最小スタンスはしていません。講習の日、やりすぎたのでしょうか?それで腰にきたのでしょうか?
【A】現時点では回答を控えます。
〔感想-S〕
最小スタンスは、とてもやりにくいです。すぐ、普通のスタンスになってしまいます。つま先の使い方も動かすと不安定になってしまいます。実技の時に私は集中できていないことに気づきました、他の人が受けた注意はすごく覚えているのですが、自分が受けた注意は忘れてしまっています。
【Q】 前に出した足の大腿前側、特に膝周りにかなり力が入ってしまいます。どこか間違ってますか? あと、前傾した方がいいのですか? 上体を立てたままでいいのですか。
【A】 最小スタンスで、大腿前側等に力が入ったり、筋肉痛になることが理解できないので、Y先生に質問しました。「前に出した足に重心がかかり過ぎているのではないか。まず最大スタンスで、重心位置を覚えて」とのこと。分からなかったら、質問して欲しいとのことです。上体の前傾はスタンスの影響を受けません。
【Q】 支点を定めない、ということの意味がいまだ分かりません。
【A】 以前、鍵盤の叩き方を例に説明したことを思い出してください。支点を定めないと特定の関節のみの可動で加圧動作や移動動作を行わないことです。それらの動作が可能な関節を交互または同時に操作する。《遠位関節は固定し、近位関節を大きく動かす》
〔感想-T〕
最小スタンスは自由度が少ない分、ねじれ、ひねりが矯正できるトレーニングだと思います。前足首の角度、テンションを忘れないように練習します。重心、身体の移動方向がわかりません。患者の肩まで向かず、頭方向でいいですか?大腿の伸筋がかなりきつかったのですが。
【A】 自支は加圧動作や移動動作に不可欠な要素です。即ち、自支を欠いて押圧法は成り立たないのです。指作りは“手指作り”と理解されているようですが、自支の為の“足趾作り”も指作りなのです。足関節操作の“足首のため”を習得する為に最小スタンスによる移動動作(下肢操作)に励んで下さい。身体動作は指一本の弱い力で制限されても、動作不能や非常にぎこちなくなります。移動動作(下肢操作)における“足首のため”は加圧動作(上肢操作)での“手首のしめ”の重要性に匹敵します。なお手指操作に匹敵する足趾操作も当然あります。考えてみて下さい。移動の動作効率を上げれば施術者の肉体的疲労は軽減され施術効率も改善されます。施術者の身体移動方向は圧点の移動方向に順ずるのが最も効率が良いと考えます。但し、加圧動作が阻害されないことが必須条件です。重複しますが、正座から立位への動作開始時に“頭の動き”を指一本の弱い力で制限され、動作が著しく阻害された事を記憶に焼き付けてください。わずかな身体操作のミスも調和を乱します。
≪ひとこと≫
2004年4月時点で〔指圧研究会・咲晩〕メンバーへ最小スタンスを指導することは実力的には早すぎることを承知していました。背伸びをしたがるメンバーをたしなめる目的で当日の講義に加えました、彼らは苦笑いするでしょうが筋肉痛や腰痛が続出したのは、彼らの基本の基礎ができていなかった証拠です。
最小スタンスに“最小スタンス独自”の基本があるわけではありません。 最大スタンスと最小スタンスでは操作は異なりますが基本は全て同じです。基本は最大スタンスの習練で習得して下さい。
筋肉痛や腰痛の方、基本を守り自己流に走らないように。まだ、ほんの、ほんの入り口付近ですからネ。
 前のページ へ
前のページ へ