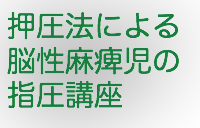![]()
情報伝達システム
情報伝達の必要性
最初に出現した生命体は、一個の細胞からなる単純な“単細胞生物”でした。
38億年後(現在)、60兆個の細胞からなる高度な“多細胞生物”に進化しました。
生命体が多細胞生物に進化するために、それぞれの細胞や器官の間に調和が必要となりました。もしも、身体が成長していく時に、骨や皮膚あるいは筋肉などの細胞が連携せずに、無秩序に成長したらどうなるでしょう。骨が筋肉や皮膚を引き裂き、飛び出してしまうような事態が生じかねません。このような事態を防ぐためにお互いの情報を伝達する必要が生じました。 〔参照:神経の発生と発達〕
ホルモンとは
細胞や器官の情報伝達のために、『化学的情報伝達物質』を作る役割を担った器官を“内分泌器官”と呼び、分泌された分泌物を“ホルモン”と呼んでいます。
〔備考:外分泌と内分泌〕
体内には、数多くの様々な目的を持つ物質(分泌物)を作る器官が存在します。これらは、分泌した分泌物を導く管“導管”の『有無』で外分泌と内分泌に分け、それぞれを『外分泌器官』・『内分泌器官』と呼びます。外分泌器官は、体温調整のための汗腺、食べ物を消化するための消化腺、子育てのための乳腺などで“分泌物のもつ役割”は異なりますが、分泌物を導管により、体外または消化管内に送り出すという共通した構造を持っています。 〔参照資料:乳房の構造〕 内分泌器官では、分泌物を(直接)体液中に送り出します。この分泌物の種類は多数ありますが、全てが情報伝達の役割を担った物質、すなわちホルモンです。
ホルモンは、驚くほど微量で作用します。20~30代の女性の女性ホルモン量は血液1ミリリットル中100~150ピコグラムです。1ピコグラムとは1兆分の1グラムですから、体重が52キログラムの女性の全血液(4リットル)中に含まれる量は、0.0000004グラムから0.0000006グラムとなります。1ミリリットル中100ピコグラムとは、ドラム缶5万本の水に1グラムの砂糖を溶かした程度の濃度です。
近年、“環境ホルモン”と呼ばれる『内分泌かく乱物質』が問題となっています。環境中に存在し生物の内分泌に影響を与える物質で、時にはホルモンと類似の作用を持つ物質です。船舶の塗料に含まれる『有機錫』もその1つですが、海水に溶け出し、近海に生息するイボニシ(貝)の生殖器に悪影響を与えています。「塗料が剥げにくい」というのが、『有機錫』を船底の塗料として使用する理由のひとつだそうです。膨大な量の海水のなかに、ごくわずかに溶け出した、塗料に含まれた『有機錫』が、近海に生息するイボニシに悪影響を与え、絶滅の回避が困難な状態に追い込んでいます。『ホルモン』や『内分泌かく乱物質』が、いかに微量で生体に重大な影響を与えるかをイメージ的に理解してください。
ホルモン異常とは、ホルモンの“分泌量の異常”を呼びます。“分泌量の異常”は各器官への誤情報となり、このことが原因となって様々な器官の調和が保てない状態を、一般に『ホルモンバランスの乱れ』とか『ホルモン失調』と言っています。
ホルモンは、特定の器官に指令を送るために分泌する物質と認識してください。成長ホルモンは成長に関わる様々な指令を伝達し、卵胞刺激ホルモンは卵胞を刺激し排卵を促します。様々なホルモンは、それぞれ担った指令を伝達します。
〔余談〕
1日に必要なビタミンCの摂取量は100ミリグラム、カルシウムなら600ミリグラム、これをダイヤモンドなどの宝石を重さを表す単位である、カラット(ct)で表すと、ビタミンCは0.5カラット、カルシウムは3カラットになり、全血液中の女性ホルモン量は・・・やめておきます。ホルモンがいかに微量かは伝わったと思います。
ホルモンというと、『ホルモン焼き』や『内臓肉』を連想される方も多いようです。なかには、「内臓からホルモンが出るから、内臓肉をホルモンと呼ぶ」と説明する方もいますが、『内臓肉』を昔は食べずに“捨てて”いました。捨てることを関西弁で“ほおる”といいます。『捨てる物』→『ほおるもん』です。ホルモンは『廃棄物』ではありません。ホルモンは、ホルモン器官から分泌される重要な“分泌物”です。
ホルモン系とは
様々な器官が情報伝達のために分泌した“ホルモン”をどんな方法で、それぞれの標的器官まで届けるか。ここで利用したのが、身体の隅々まで行っては戻る、血液の流れ(閉鎖循環)でした。脳では遠く離れた卵巣に排卵を促すために分泌した“卵胞刺激ホルモン”に『卵巣』と宛名を書き、血流に乗せて届けています。
このように、情報伝達物質(ホルモン)を血流(血液の閉鎖循環)に託すシステム で標的器官へ伝達する手段を用いる器官を“ホルモン系”と呼んでいます。
〔ホルモン分泌器官とホルモン系は混同しやすいので、注意してください〕
神経系の獲得
脳から卵巣へ、4週に一度の排卵を促すホルモンは、平均秒速1センチメートルの血流に乗せて伝えても十分に機能します。血流の具合で、ホルモンが遠回りして卵巣に届いても、脳の卵巣コントロールに支障が生じる程ではありません。しかし、心臓コントロールのように、敏速で正確な反応が必要な情報(ホルモン)の伝達を最速でも“平均秒速1センチメートル”、さらに気ままな血液循環に委ねていたのでは、脳が敏速かつ正確に心臓をコントロールすることは不可能です。
そこで、脳が自在に心臓をコントロールするために、従来の血液循環システムにホルモンを託す方法ではなく、“新たな情報伝達システム”が必要となりました。
神経系とは、従来の血液循環にホルモンを運ばせる“ホルモン系”のシステムとは異なり、細胞体から標的器官まで突起を伸ばし、標的器官にホルモンを直接受け渡すという、全く“新たな情報伝達システム”です。このシステム獲得により情報伝達速度は“ホルモン系”の100倍に跳ね上がりました。さらに、ダイレクトな情報伝達システムの持つ精度は桁違いと言えるほど画期的なものとなりました。
神経は、構造の違いで、無髄神経(自律神経)と有髄神経(知覚・運動神経)に分類します。有髄神経とは、神経細胞から伸びる繊維(神経線維)にミエリン鞘と呼ばれる、絶縁体を鞘としています。情報伝達の速度は無髄神経(自律神経)で血流の100倍を確保。さらに、有髄神経(知覚・運動神経)では血流の10,000倍(秒速約100メートル)のスピードを獲得することができました。
〔備考:神経症と神経の病気〕
神経症と“神経の病気”は混同されやすいのですが、神経症は、心理的な原因で起る精神の病気で、神経の異常によって起る“神経の病気”ではありません。
キーワード
ホルモンとは、『化学的情報伝達物質』です。ホルモン分泌器官とホルモン系は混同しやすいので注意してください。神経細胞は、一種のホルモン器官です。
神経細胞には、ホルモンを放出する機能と受け取る機能があります。無髄神経と有髄神経は構造の違いにより分類し、情報の伝達速度が100倍異なります。
自律神経は無髄神経、知覚や運動神経は有髄神経で構成されています。
ホルモン系・無髄神経系・有髄神経系は何れも情報伝達手段ですが、身体は、それぞれに特徴がある情報伝達システムを実に効率良く使い分けています。
 前のページ へ
前のページ へ