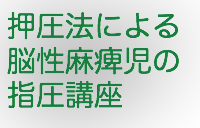![]()
アプローチの前に
【窓や名札との関わり方】
〔性格について〕でも概説しましたが、人の心はドーム(塔)の中心に隠されたコア(核心)に似ています。このドームには、それぞれ(そのときの立場や関係)を表す名札が付いた多くの窓があります。人と人の関係を“人間関係”と呼びますが、人間関係とは、“人との間”に関する係わりだと考えます。社会生活において、人との関わり方、すなわち“適切な距離”を保持しなければ、“間抜け”や“間違い”が生じます。このとき、自分や相手の“名札”を確認し、TPOに応じた適切な対応が必要です。さらに、これらの窓は“立場や関係”を表す名札専用で、自身や相手に関わらず異なる名札で関わってはいけないようです。
【『えのき』との関係】
『えのき』は教師猫の娘で『えのきママ』は教師猫の妻です。教師猫にとって『えのき』と『えのきママ』のどちらが近いのでしょう。それは、その時、教師猫が立っている窓の名札と関わります。教師猫の窓にも父・夫・雄・指圧師など様々な名札があります。教師猫の“父の窓”からは、『えのき』の“娘の窓”は最も近い位置にあります。教師猫の“雄の窓”を覆うように、最も近い位置に『えのきママ』がいます。教師猫が“雄の窓”を全開にすると、多くの“雌の窓”が見えますがなぜかブラインドは閉じられているようです。しかし、どんなに探しても『えのき』がいません。『えのき』も雌のはずなのですが、『えのき』の“雌の窓”どころかドームさえ見つけることができません。教師猫の“父の窓”と“雄の窓”の配置を見たら、両者はドームの両極に位置していました。教師猫の“雄の窓”からは、『えのき』は永遠に最も遠い存在です。
【適切な距離について】
一般の社会生活においては、人との関わりに“適切な距離”を保持しなければ、“間抜け”や“間違い”となりトラブルが生じやすくなります。気心が知れている間柄では、相手からの『NO』を受けてからの対応も可能ですが、初対面の場合では改善が困難となる場合も少なくありません。一般的で有効な対策は“近づかないこと”ですが、治療家が患者に近づかなくては何もできません。時として、治療家は患者のドーム(塔)の中心に隠されたコア(核心)まで、“招き入れられ”て、触れる必要があります。
多くの動物が“適切な距離”を保持し、ニアミスなどによる無用な争いを避ける様々な手段を用います。なかでも、発声は見通しがきかない場所やリアルタイムで“適切な距離”を保持する有効な手段です。発声を進化させコミニュケーションの手段と用いるものも少なくなく、群れる動物でより顕著のようです。
【挨拶の意味と真意】
『挨拶切る』とは、人との関係を絶つことを意味します。発声により自己の存在や所在を相手に知らせることは、こちらが相手に対し不意打を行なわないことの証であり、“無益な争いを避ける意思”がこちらにあることを相手に明確に伝えることができます。群れる生活において、劣位な者が先に“挨拶”をします。この行為は、優位な者の警戒心を緩和させる効果があり、劣位な者の有効な自己防衛手段となります。いつしか、群れの中で劣位な者が先に“挨拶”をし、優位な者が返すというルールが慣習化されました。優位な者への敬意を表す作法の有無は、劣位な者を悲惨な状況に追い込むことも稀ではありません。優位な者の“挨拶”は意思に準じやすいのですが、劣位な者の“挨拶”は大半が自己防衛手段であり、意思とは無関係な要素が多く含まれます。優位な者ほど劣位な者の真意を読み取ることは困難です。
 前のページ へ
前のページ へ