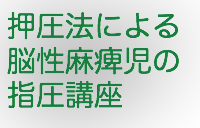![]()
廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)について
廃用性萎縮とは、生体の器官が使われないために痩せ、その機能が低下することで、〔不動性萎縮〕とも呼び、 〔不動性萎縮の防止や心得〕で概説しましたが、ほとんどの器官は、『使わなければ、使えなくなってしまう』性質を持っています。廃用性萎縮は病気ではありません。その生理的な“性質”について概説します。
重要な廃用性萎縮
高等動物ほど未熟な状態で生まれ、生後成長に伴い様々な能力を獲得します。〔正常な未熟児〕でも概説しましたが、人は巨大な脳を持ったことにより、胎生期において様々な能力獲得に対する準備と生後における機能の学習が不可欠となりました。しかし、胎生期に準備した能力を終生維持することやそれらの機能をすべて獲得するためには膨大なエネルギーが必要です。そのエネルギー獲得機能を確保するためのエネルギーは・・・(難解となりますので話題を変えます)
廃用性萎縮について負のイメージを持たれることが多いようですが、生存競争において、不要な能力を温存することは生命活動に有利ではありません。廃用性萎縮は、生命活動において“無駄を省く”という重要な役割を担っています。
二次的な廃用性萎縮
廃用性萎縮は、生命活動の効率向上のために“無駄を省く”という重要な役割を担っています。しかし、この機能が二次的に作用した時“必要な機能を低下させてしまう”という生体にとってきわめて厄介な状態が生じてしまいす。
臨床現場において“無駄を省く”廃用性萎縮と“必要な機能を低下させてしまう”廃用性萎縮の見極めは重要です。特に、疾患に伴う二次的廃用性萎縮の予測が予防や早期治療に重要となります。脳性麻痺児の運動機能障害は脳の神経障害とか脳性疾患の後遺症と論じられます。このことが誤りではありませんが、脳性麻痺児の運動機能障害の現実は、脳の神経障害や脳性疾患の後遺症等に伴う二次的廃用性萎縮で、“必要な機能を低下させてしまう”廃用性萎縮への対応の不備が非進行性である脳性麻痺による運動機能障害を進行させる原因となっています。〔詳細や具体例は講義で説明します〕
二次的な廃用性萎縮への対応
脳性麻痺による運動機能障害を進行させる原因となる二次的廃用性萎縮への対応法として最も効果的なのは、押圧法による“過緊張緩和術”だと考えます。
押圧法には種々の“過緊張緩和術”があり、それぞれ高度な押圧技術を必要としますが、『親子というごく自然で特別な関係』を利用した、押圧法によるわが子に対する腹部指圧は、安全で有効な二次的廃用性萎縮防止と治療手段です。
次のページへ
 前のページ へ
前のページ へ